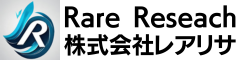4月4日、中国は米国による「相互関税」政策への対抗措置として、7種の中・重希土類――サマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ルテチウム(Lu)、スカンジウム(Sc)、イットリウム(Y)――に対する輸出管理措置を発表し、即日施行した。この措置は輸出を全面的に禁止するものではないが、中国政府が輸出許可の発行数を制限できることから、実質的な供給制限と同様の効果をもたらすと見られている。
米国メディアによれば、この規制は米国の防衛産業、特に次世代制空戦闘機「F-47」の開発に深刻な影響を及ぼす可能性がある。F-47は第六世代戦闘機として構想されており、従来のF-22やF-35を開発したロッキード・マーチンではなく、民間航空機で知られるボーイング社が契約を獲得したことで注目を集めた。しかし現在、開発は設計段階にとどまっており、試作機の製造にも着手していない。
こうした次世代戦闘機の開発には、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムといった希土類元素が不可欠である。これらは高性能レーダー、電子戦システム、アクチュエーター、電動モータなどに使用され、ステルス性能の維持、高温環境下での磁力安定、精密誘導や通信機能の確保といった先端技術の根幹を成している。また、構造材としてのチタンや、耐熱合金に用いられるタングステン、ニオブなどの金属資源も中国の供給網に大きく依存している。
実際、すでに実戦配備が進んでいるF-35戦闘機においても、1機あたり約400キログラムの希土類が使用されているとされ、その安定供給は中国からの継続的な輸出に大きく左右されている。F-35に搭載される高性能レーダーもガドリニウムなどの素材に依存しており、規制が長期化すれば、生産の持続性に重大な影響を及ぼしかねない。
一方で、中国では航空産業の近代化が急速に進んでおり、「殲-36」および「殲-50」とされる第六世代戦闘機の開発が進行中である。両機は2030年以前の実戦配備が視野に入っており、中国が世界で初めて2機種の第六世代戦闘機を同時運用する可能性も浮上している。
このような状況の下、中国によるレアアース輸出管理の強化は、米国の防衛装備開発にとって深刻な制約となり得る。レアアースの採掘や精製には高度な技術、膨大なコスト、そして深刻な環境負荷が伴う。特に重希土類については、中国が世界の生産のほとんどを担っており、代替供給源の確保は極めて困難とされる。